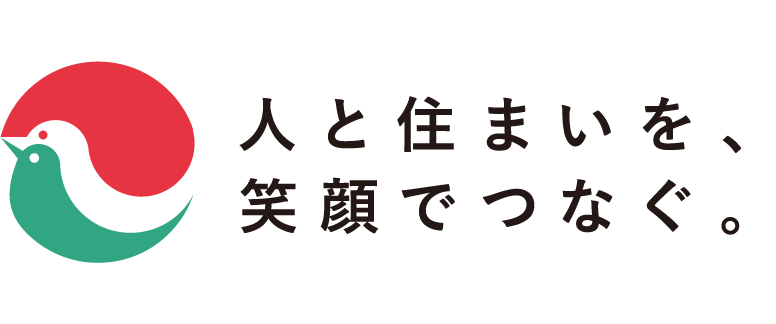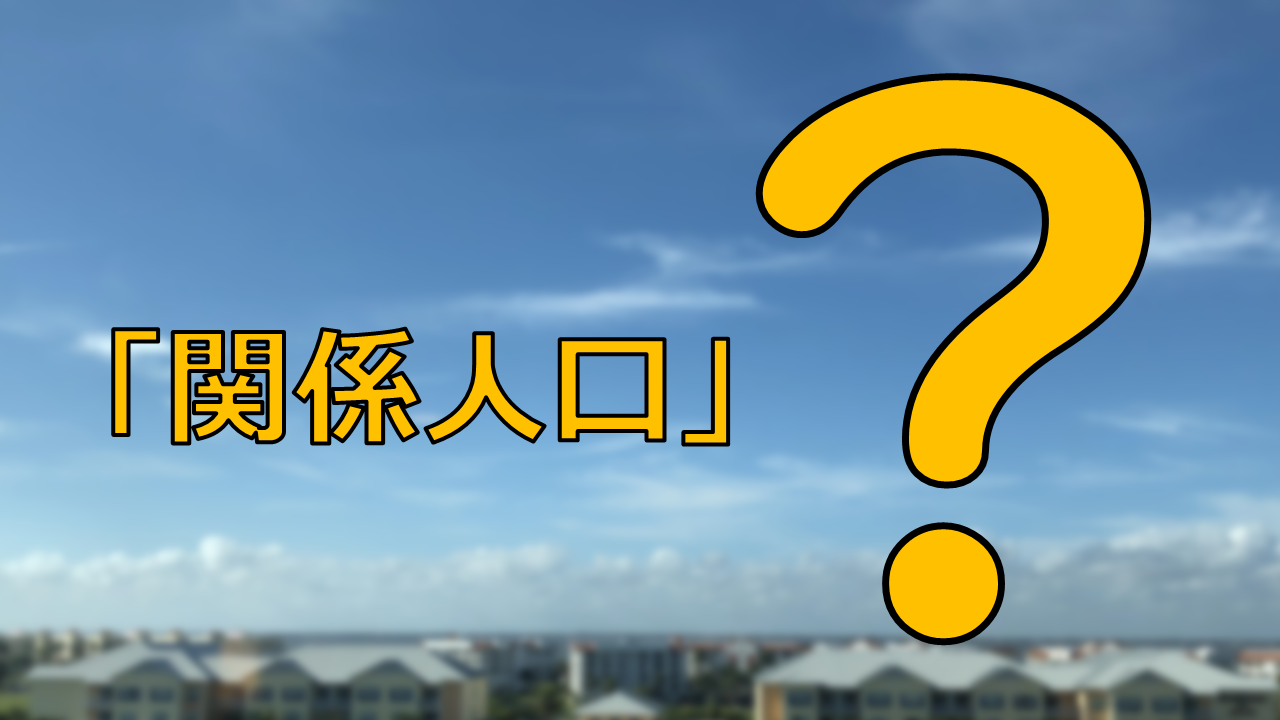
移住でも観光でもなく、日常生活圏や通勤圏以外の特定の地域と継続的かつ多様な関わりを持つ「関係人口」という概念が昨今注目されています。
総務省のホームページによりますと、「関係人口」を以下の通り定義しています。
「関係人口」
移住した「定住人口」でもなく、観光に来た「交流人口」でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のことを指します。 地方圏は、人口減少・高齢化により、地域づくりの担い手不足という課題に直面していますが、地域によっては若者を中心に、変化を生み出す人材が地域に入り始めており、「関係人口」と呼ばれる地域外の人材が地域づくりの担い手となることが期待されています。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/kankeijinkou.html
地方創生の活性化に向けて、この「関係人口」の重要性に着目されていますが、これまでは規模などの実態は十分に把握されていませんでした。
そこで、国土交通省では9月に関係人口の規模を把握するための実態調査を行い、2月18日にその結果が公表されました。
http://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku03_hh_000193.html
特に資料2「関係人口の実態把握(補足資料)」には、「関係先が移住先としてどうか」や、東京圏・大阪圏の回答者が国内のどこの自治体の関係人口であるかが地図で表示されている点など、とても興味深い資料となっていますので参考にされてください。
なお、今回の調査は試行的に三大都市圏居住者を対象に行われていますが、国土交通省では来年度以降は全国規模の広範囲の調査を実施する予定とのことです。